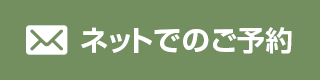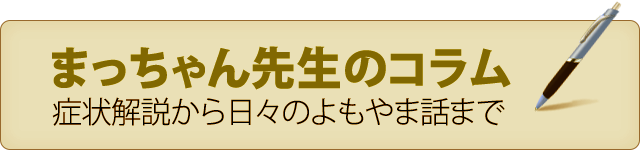神経筋肉疾患
脳卒中(脳梗塞・脳出血)(中風)の概要
脳血管障害は中医では中風や卒中・類中と呼ばれています。
本病は、一過性脳虚血発作・脳卒中・椎-脳底動脈供血不足・脳血管性痴呆・高血圧性脳病・脳動脈瘤・脳動静脈奇形・脳動脈炎・その他動脈疾病・脳静脈疾患・脳静脈洞及び脳静脈血栓形成などに分類されます。その中の脳卒中にはクモ膜下出血・脳出血・脳梗塞が含まれ、更に脳梗塞にはアテローム性動脈硬化症(粥状硬化症)・脳塞栓・出血性梗塞・無症候性脳梗塞・その他原因不明の脳梗塞に分類されます。
中医と現代医学の本病の発病誘因に対する認識は同じで、季候の急激な変化、過度な苦労、激しい感情の変化、不当な力の使い方などが本病の発作誘因とされています。中医学での認識は、本病は上述の誘因によって、化火動風が起こり、陽気の勢いが盛んになり、気血が逆乱することで風・火・痰・気・?が産出され、清竅を塞ぎ、神明が宣発の作用を失うと中風になるとされます。現代医学では上述の誘因によって脳血管障害に至るとされています。
その急性期の病理変化は脳組織の虚血・出血・酸欠・脳水腫・破壊・軟化と多部位における毛細血管周囲の滲出で、後期では瘢痕や嚢腔が形成されます。針刺治療は脳部の血液循環を促進し、脳組織の酸欠を改善し、脳水腫の吸収を加速させます。その結果、脳組織の再生効果を顕著に向上させます。よって、針刺は脳血管障害で最も有効な治療方法の一つです。とりわけ石学敏院士が創立した“醒脳開竅針刺法”は急性期の脳血管障害の治療で、竅閉神匿の発病理論に重点を置き、醒脳開竅針刺法の治療方法を制定しました。臨床では顕著な治療効果を収めています。
症状
中風は病位に深浅があり、病情に軽重があり、標本虚実にも前後緩急の違いがあります。よって臨床ではよく中風を中風前兆・中経絡・中臓腑および中風後遺症に分類します。
(1)中風前兆
眩暈、半身あるいは一側の手・足の麻木無力。
(2)中経絡
突然発症した顔面麻痺、言葉がうまく話せない、半身不随。
(3)中臓腑
閉証:突然倒れる、人事不省になる、口を強く閉じる、両手は固く握る、大小便が出ない、舌が巻き縮まる、併せて顔面紅潮、呼吸が粗い、痰鳴がする、口臭、発熱、ずっと動いて止まらない。
脱証:突然倒れる、人事不省になる、眼や口が開いている、呼吸はかすか、手は開き四肢は冷たい、汗がたくさん出て止まらない、大小便失禁、肢体は無力、舌が出ている。
(4)中風後遺症
顔面麻痺、失語、失明、上肢硬縮或いは軟らかく無力、手指は固く握る或いは開閉が出来ない、肩関節が痛く挙げる事ができない、下肢は硬縮或いは軟らかく無力、足内反或いは下垂、便秘、小便が出ずらい或いは漏れる。
鑑別
脳血管障害の主要な臨床症状は突然発病し、脳全体の症状から神経系統の決まった所見が見られます。たくさんの疾病で脳血管障害の基本的な症状や所見が出現します。よって脳血管障害の患者を受け入れたときにはしっかり鑑別診断を進めなければなりません。
(1)感染性脳炎・脳膜炎・脳膜脳炎
急性や亜急性に発病し、脳炎は意識障害が主で常に癲癇発作を伴います。検査では多病巣性脳損傷の所見が見られます。以上の症状や所見は脳血管障害のものと似ています。その鑑別点は本類の疾病の多くは発病時に頭痛や全身の不快感などの前駆症状を伴い、疾病過程では全身性の感染中毒症状があります。脳炎では頭痛が突出しているのが主で、脳膜刺激症状が明確に見られ、脳脊髄液や脳CTの検査が鑑別診断の重要な根拠となります。
(2)脳腫瘤
癌転移は肺部からのものが多いのですが、時には神経系統の症状と比較的早く進展する意識障害が始めの症状のことがあります。発病前には頭痛や癲癇発作などの症状が見られますが、本病は発病が緩慢で、眼底には乳頭水腫、網膜に火焔状出血などが見られ、慢性脳内圧力亢進の所見が見られます。脳CT及び肺部のX線検査にて鑑別する事ができます。
(3)脳外傷と外傷性脳内血腫
脳外傷は明確な外傷歴があり、外傷後すぐに意識障害になり、併せて局在性の神経所見が見られます。脳CT検査にて確定診断と鑑別が出来ます。
(4)脳膿腫
脳内圧力上昇の症状及び神経系統の局在的な損害症状が見られます。重度の場合は脳ヘルニア或いは脳膿腫破裂に化膿性脳室管炎の合併或いは脳膜炎の合併により意識障害が引き起こされます。但し本病の多くは青中年に見られ、中耳炎・乳突炎が最も良く見られる感染源で、発病は緩慢です。症状は全身の感染中毒症状及び血液検査から鑑別診断が可能です。
(5)中毒性疾病
毒物は主に消化器・呼吸器・皮膚粘膜を通して体内に入って、中毒性脳病を引き起こします。症状は局在性神経系統の所見が見られます。肢体の麻痺は一肢麻痺或いは軽度麻痺で、癲癇発作・錐体外路症状・小脳症状・脳神経麻痺などの症状が併せて見られることがあります。但し上述の薬物による急・慢性中毒病歴があり、麻痺症状は中毒症状の一つです。これによって鑑別診断します。
(6)急性播種性脳脊髄炎
本病の発病は急で、病変はびまん性、脳・脊髄や末梢神経を巻き込みます。症状は片麻痺や単麻痺、重度の脳損傷が見られ、重度の脳損傷では意識障害と癲癇発作が引き起こされることがあります。脳髄膜刺激症状も見られます。本病と脳血管障害の鑑別方法は、発病は児童や青少年に多く、発病前にある種の予防接種を受けたものやある種の伝染病を罹ったといったものが多く見られます。
鍼灸治療
(1)治則
中風の異なった病機から、異なった治則と配方を採用します。
中風前兆:
調神通絡(神を整えて気血の流れを良くする)
中経絡:
醒脳開竅・疏通経絡(脳を覚まし意識をはっきりさせる、経絡の流れを良くする)
中臓腑(閉証):
開竅啓閉(閉じている竅を開ける)
中臓腑(脱証):
回陽固脱・醒神開竅(陽気を戻し力をつける、神を覚まし意識をはっきりさせる)
中風後遺症:
疏通経絡・矯偏和絡(偏りを矯正し経絡を協調させる)
(2)配方:省略
(3)操作:省略
(4)治療頻度・期間
急性期(発病1週目~2週目以内):
毎日二回針刺する。10日を一療程とし、三療程は続けて治療する。
回復期(発病2週目~6ヶ月):
毎日二回針刺する。10日を一療程とし、3~9療程は続けて治療する。
後遺症期(発病6ヶ月以上):
毎日二回針刺する。10日を一療程とし、6~12ヶ月は続けて治療する。
(治療頻度や治療期間は理想的には上記ですが、一般的には、急性期では治療頻度は毎日1・2回、治療期間は最低1ヶ月。また、回復期では治療頻度は週2・3回で、治療期間は1~3ヶ月です。後遺症期では治療頻度は週1・2回で、治療期間は6~12ヶ月行ないます。また、予防や症状のコントロールを目的とした場合には、週1回もしくは2週間に1回の治療を長期間行ないます。どの時期でも、治療頻度が多いほうが治療効果は高いのですが、現実的な治療頻度を選択する事が望ましいでしょう。)
治療理論
脳血管障害は中医では中風・卒中と呼ばれます。石学敏院士は昔からの方法と現代科学技術を融合させて一体として採用し、長年の臨床と研究から中風は“上実”、即ち脳竅が塞がることで、その原因は全て肝腎の虧虚、即ち“下虚”によるものであると認識しました。脳は神の府で、神が傷つけば気を使う事が出来なくなります。加えて風邪が痰・火・気・血を挟みもろもろの根本が逆乱し、“竅閉神匿”の病理転機を引き起こます。竅閉神匿し神不導気に陥り中風が発生します。“竅閉神匿”の病機を根拠に、“醒脳開竅”大法が起こされました。
治療上では、開竅啓閉(穴を開け閉じたものを開く)し、元神の府を改善させます。---大脳の生理機能が主で、取穴では陰経経穴が主で、併せて手技操作を行います。古代の医家は“正気本虚、風阻経絡”が多く、“疏経活絡、風取三陽”が中風を治療するとされたために、針刺の施術では“補法”が主とされていました。石氏は“神竅匿閉”の病機と“啓閉開竅”の針刺法の確立に基づいて、針刺施術は“瀉法”を以って主としました。繰り返し行なわれた実験によって、針刺法の四大要素が創立され、長年の臨床と研究を通して治療効果が最も顕著であることが証明されています。
近年の大量な基礎実験研究により、醒脳開竅針刺法には以下の作用があることが証明されています。①虚血性中風患者と高粘度血症動物の血液流変の改善、局所脳組織の血流増加、②虚血性中風患者の脳動脈血流動力及び微小循環の改善、③脳虚血と再環流時に作られる遊離基(フリーラジカル)による損傷の抑制、④実験マウスによる脳組織血流の増加、脳組織超微小結合の改善、脳水腫の軽減など。
症例1
一過性脳虚血発作
主訴
頭暈・右半身運動無力の断続発作3日
病歴
患者は高血圧病歴を10年持っており、血圧変動は21.3~28.0/12.0~16.0kPa(160~210/90~120mmHg)の間で、断続的に降圧薬を服用していた。6月5日早朝頭暈を自覚し、眼の前が暗くなり、頭が重く足が軽く感じ、すぐに右上下肢の動きに力が入らなくなった。横になりたいと思い、横になって30分休息したのち、症状は消失した。午後2時にまた発作が一度あり、症状は午前と同じだった。すぐに当院救急外来に来院し、観察したところ、血圧は22.7/13.3kPa(170/100mmHg)であり、プロメタジン塩酸塩を筋肉注射し、50%葡萄糖60mlを点滴静脈注射し、病状が安定したあとで入院した。
検査
精神弱、面色無華、両目無神、右上下肢軟弱無力、動作緩慢、歩く時は介抱が必要、舌質淡、苔薄白、脈弦細。瞳孔(-)、軽度口歪、両肺(-)、心音有力、主動脈弁第二心音亢進、肝脾触れず、四肢生理反射存在、病的反射みられず、右側肢体筋力は共にⅢ級。血圧21.3/13.3kPa(160/100mmHg)
印象
(1)中医:中風前兆
(2)西医:一過性脳虚血発作
治則
醒脳開竅(脳を醒まし意識を回復させる)
疏通経絡(経絡を通じさせる)
滋補肝腎(肝腎を補う)
処方
内関、人中、三陰交、極泉、太衝、絶骨など
治療経過
上記穴を毎日二回針をする。一回目の治療後患者の眩暈は軽減し、三回目の治療後右上下肢の動きに力が入るようになり、頭暈は基本的には消失、続けて五回治療したのち、諸症状は消失、四肢の運動は正常化し、臨床的治癒となった。
日本では一日二回針治療することは難しいですが、一日一回でも十分に効果は期待できます。現代医学的な服薬治療も当然必要ですが、針治療を併せて行うことで、回復を促したり、再発を抑制したりする効果が期待されます。
症例2
脳梗塞
主訴
左半身不随に伴い言語に流暢さを欠く、13日
病歴
患者は9月12日夜間に風と寒さにあたり、翌日早朝に左半身不随が出現した。精神ははっきりしていて、四肢は麻痺し、話は遅く、歩くことができなかった。すぐに某医院観察室へ送られ検査した。腰椎穿刺報告:脳脊髄液は無色透明、糖五管(+)(訳注:中国には糖五管という試験があるようなのだが詳細は不明。脳障害の有無を調べるもののよう)、よって「脳障害」と診断。抗血栓・抗感染の治療を行い、12日後には病状が安定。その時点での状態は、精神ははっきりしている、口が歪んでいる、患側四肢は自分で動かすことができない、言語は流暢さを欠く、頭痛・眩暈は無い、大小便は制御できる。高血圧の病歴は否定。9月23日に当科で治療のため入院した。
検査
血圧32.0/16.0kPa(240/120mmHg)、脈拍60回/分、神清体痩、左側中枢性顔面神経麻痺、言語欠流暢、両側頚動脈拍動対称。心音低鈍、A2>P2、心拍調律正常、左肺呼吸音粗い。腹軟、腸鳴音低。左上・下肢弛緩性麻痺、生理反射は全て(+)、左バビンスキー徴候(+)。舌質紅、苔黄膩而乾、脈弦細。
印象
(1)中医:中風(中経絡)
(2)西医:脳梗塞、高血圧
治則
醒脳開竅(脳を醒まし意識を回復させる)
滋補肝腎(肝腎を補う)
疏通経絡(経絡を通じさせる)
処方
内関、人中、三陰交、極泉、尺沢、委中、風池、上星透百会など
治療経過
1週間の治療後、左下肢伸展挙上高は40°、左上肢は肘の屈曲可能、挙上して胸を平らにできる、言語ははっきりしている。2週間後、介助しながら歩いたり走ったりでき、続けて一人で歩いたり走ったりできるようになる、左上肢は頭の上まで挙上できる、左手握力は少しの違いがある。4週間後、左右四肢の機能は正常、言語ははっきり。完全治癒したため退院した。
ここでは鍼灸治療以外の治療についてあまり触れていませんが、当然現代医学的に検査をして必要な治療はやっています。誤解して欲しくないのは、鍼灸治療が良いのは言うまでもありませんが、鍼灸治療だけで良いと言う話では無く、医学の東西を問わず、使える治療は使うということです。
この症例はほぼ完全に治癒した例ですが、こういうケースは珍しい訳ではなく、比較的よく見かけます。ちなみに、この患者さんは67歳です。